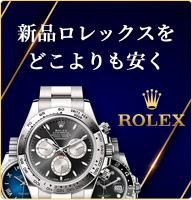会社を設立しようとする経営者の頭を悩ます問題の一つが資金です。会社や事業を立ち上げようとする会社設立準備中の期間は、収入がない状況になります。また、会社設立する段階では、店舗や事務所を賃貸する事やまたその設備などを購入するなどまとまった設備投資費用が必要になります。そして、会社設立後の事業が安定するまでは、売り上げなどで入ってくるお金が増えますがそれより固定費の支払いなどで出ていくお金のほうが多い状態が続きます。
そのため、創業にはまとまった資金が必要になります。これらは、設立に向けて貯めていた自己資金だけでは足りない場合も出てきます。そんな時に助けになるのが、金融機関や政府系機関から融資などによる資金調達=創業融資となります。
今回は、会社設立の際の資金調達について、特に利用される方も多い日本政策金融公庫と制度融資について特徴とメリット・デメリットの比較や手続きについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
1 創業融資とは

創業融資は、会社設立に必要な事業資金を融資=借入する事をいいます。創業時には前述のとおり、資金を必要とする場面が多くなります。事業を行う上で、資金が無くなるという事は事業の停止を意味します。そのため、常に資金は必要になり、現在の資金量と今後必要になる資金量を予想して、適切な資金計画を立てておくことは経営者の必須の能力になります。
そして、仮に将来において必要になる資金に対して、現在から考える将来の資金めどが不足している場合には、資金をなにがしかの方法で調達する必要が出てきます。そして、資金調達の選択肢の1つが融資になります。
1-1 創業時の資金調達方法
創業時に資金を調達する主だった方法は以下のようになっています。なお、どのような資金調達を活用する時も同じですが、資金が無くては困る状況になってから、調達方法を探すのは危険です。“転ばぬ先の杖”で、資金が必要ではない段階から複数の資金調達方法を準備しておくことが賢明です。
≪創業時の資金調達方法≫

①助成金や補助金
助成金と補助金は、返済する必要がないお金である点が共通事項になります。また、助成金も補助金もそれを受け取るという事は、会社として適切に事業を行っている事を国や地方自治体が認めたことになります。そのため、その後に金融機関などの民間機関からの融資を受ける際にはプラス材料になります。

〇助成金
助成金とは、厚生労働省が管掌する雇用に関連した助成のための支援金になります。助成金は、その支給要件を満たしている企業や事業主には原則として給付を受ける事が出来ます。助成金は、雇用に関わる給与などの支払いを行った後に、その一部ないしは全てを後から申請する事で受け取る事が出来ます。
助成金は、要件を満たして申請すれば受け取る事ができる点は最大のメリットですが、給付を受けるまでに半年以上の期間が必要になる点には注意が必要です。
主な助成金は、以下のような助成金があります。いずれも詳細は厚生労働省のホームページで確認できます
〇補助金
補助金とは、国や地方自治体がそれぞれの公益性に照らし合わせて一定の条件に合致した企業や事業主が給付される金銭になります。補助金は、主に創業支援や新規事業支援などの国策の促進を行うための手段の一つです。
助成金との違いは、補助金には予算枠があり、その予算枠を使い切ってしまうと、条件に合致した企業であっても補助金の支給を受ける事が出来ない点になります。また、補助金の予算はあらかじめ各自治体で組まれており、4月から5月に公募される事など公募期間が1ヶ月程度になっている事が一般的になっています。そのため、事前に準備を行い、公募が開始した段階で申請ができるようにしておく必要があります。
補助金は助成金と比較すると種類が豊富であり、支給額も数百万円からと金額が大きいなどのメリットがあります。一方で、助成金と同様に申請から支給までに1年程度の期間が必要になるため、緊急的な資金調達方法には向きません。
創業時に関わる補助金としては、主に地域創造的企業補助金(創業支援等事業者補助金)があります。
地域創造的企業補助金は、創業者を支援するための補助金制度になります。市区町村の支援を受けながら、事業計画書を作成・申請を行います。一般的な条件は、『補助金公募開始日より後に創業するまたは操業予定の企業や事業主である』『1名以上の従業員雇用を行う(予定)』『認定市区町村の創業支援を受ける』の3つになります。
②融資
融資は、返済義務のある金銭を借りる事をいいます。また、一般的には借りたお金である“元金”とその元金の残高にかかる“金利”をあわせて返済していく事になります。また、創業時などの信用力が少ない段階においては、保証会社に支払う“保証料”も必要になる場合があります。
創業時の融資に主にかかわる金融機関等は以下になります。
・信用金庫
信用金庫の目的は地域社会の繁栄となります。そのため、地域の活性化につながる中小企業や個人事業主を主な取引先としている金融機関になり、銀行などよりも柔軟な融資姿勢を示します。
・日本政策金融公庫
日本政策金融公庫の目的は、日本国政府の経済政策に沿って“日本経済を活性化”させる事になります。そのため、銀行などの金融機関が融資を受けにくい創業者や中小企業への融資を積極的に行っています。
創業者を支援する事を目的とする融資制度として『新創業融資制度』が最も知名度があります。その他にも『新規開業資金』や『女性、若者/シニア起業化支援資金』や『中小企業経営力強化資金』などがあります。(詳細は後述します。)
・信用保証協会
信用保証協会は、信用保証協会法に基づき中小企業や個人事業主の金融円滑化を目的に設立されています。信用保証協会は金融機関が融資を行う際の、中小企業や創業者の保証力を補うための保証人となります。信用保証協会を利用した融資の方法の一つが『制度融資』になります。(詳細は後述します。)
・ノンバンク(ビジネスローン専門業者や消費者金融等)
ノンバンクとは、預金受け入れの業務は行わず、融資やクレジットなどの貸付サービスを専業とする金融会社をいいます。ノンバンクの目的は利益であり、融資などを事業としているため、比較的スピーディーかつ柔軟な融資を行います。一方で、銀行や日本政策金融公庫などと比較すると、金利が高い面がデメリットになります。
ビジネスローンとして会社を主契約者とする場合もありますし、社長自らが個人で消費者金融から融資を受ける場合もあります。
・個人の私的借入
創業時に親族や友人から借りる事をいいます。人間関係に依存しビジネスだけで割り切れない関係に依存するため、できるだけ最後の手段とすべきです。借入を行う際にはトラブルを避けるため、金銭消費貸借契約書を作成する事は必須です。
③出資
出資とは、株式会社が発行する株式と交換に投資家から資金を受け取る事などをいいます。この場合の資金は、返済の必要はありません。株式を受け取った投資家は、株主になります。株主は、企業が利益を上げた場合などに配当金を受け取る権利や株主総会を通じてその会社の経営に参加できます。
一般的な会社で投資を受ける場合には、取引先や顧客などから投資家を探す必要があります。現在は、ベンチャーキャピタルやクラウドファンディングなどの方法で出資を受ける事も出来ます。
ベンチャーキャピタル(VC)
ベンチャーキャピタル(Venture Capitalといい、以下は「VC」と呼ぶ)とは、未上場企業に対して出資を行う機関をいいます。世の中にまだその価値が知られていないために価値が低くなっている会社へ出資し、上場などを通じてその会社の価値が高くなった際に売却して、売却分と出資額の差額の利益の獲得を目指しています。
VCから出資を受けるメリットは、VCからお墨付きを得たという社会的信用力や注目度の向上を得られる事や、成長していくための知恵や支援を受ける事が出来ます。一方で、デメリットは経営者とVCのその会社の経営方針が一致しない場合には経営スピードが落ちます。また、VCにこれ以上会社の価値が上がらないとなった場合には、その会社の経営が苦しい状況であっても出資を引き揚げられるリスクがあります。
また、VCから出資を受けられる会社は、“成長見込みがある会社”に限られます。そのため、資金調達手段の難度は非常に高くなります。一方で成長見込みがある事業ではあるものの、その成長資金が不足している場合には根気強く出資してくれるVCや出資者を探す事が必要になります。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、2000年代からスタートした比較的新しい資金調達方法の一つです。インターネットを通じて、広く出資や支援を募る事を行う事が出来ます。2011年に日本で初めてのクラウドファンディングサービスREADYFORがサービスを開始しており、現在では様々な会社が同様のサービスを手掛けています。
クラウドファンディングの方法は、投資家を募って株式投資を受け入れる投資型の他に、モノやサービスを購入してもらう代わりに事前に決めた購入者へのリターンを提供する“購入型”や支援者が寄付できる“寄付型”等があります。
クラウドファンディングは、多額の資金を一気にまとめて集める事は出来ないかもしれませんが、支援者の数を増やす事は可能です。但し、事業や会社に人を引き付ける魅力がある事が前提になります。
④その他
資金調達方法ではありませんが、起業した経営向けの共済である『小規模企業共済』について解説します。
小規模企業共済
小規模企業共済は、会社経営者や個人事業主がその会社や事業を廃止・退職する際に受け取る事ができる積立金に応じた給付金制度になります。企業に勤めているサラリーマンが受け取る退職金に代わるものが小規模企業共済になります。国の行政法人である中小企業基盤整備機構が運営を行っており、132万人以上の小規模企業の役員や経営者や個人事業主が加入しています。
1-2 創業融資とその必要性
創業時にできる資金調達において、返済の義務がないという点においては助成金・補助金や出資が有効な資金調達方法です。一方で、一般的な企業が資金を必要な時に必要な金額の資金調達ができる方法かというと、疑問符がつきます。そのため、多くの企業が創業融資を活用ないしは検討しています。
創業融資は、創業時に必要とする資金を借入によって補う事をいいます。融資を受けるには貸しても返済してくれるであろうという信用が必要です。しかし、創業時の企業には、信用を作り出すための“事業実績”も“返済実績”もありません。そのため、創業時に融資先を見つける事は簡単ではありません。
創業融資の代表例は日本政策金融公庫と信用保証協会による制度融資となります。ここからはこの二つの融資方法についてより詳細な解説をしていきます。
1-3 日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、経済や産業の発展と国民生活の安定を目的として、国の金融政策に沿った民間サービスが消極的な部分をカバーしています。
例えば、事業実績がない企業に融資を行う創業融資もその一つです。
日本企業の廃業の多くは経営者の高齢化によるものになるので、廃業事態に歯止めをかける事が難しい状態です。そのため、新規企業の参入が経済や産業の発展には必須です。しかし、前述のとおり民間の金融機関が融資を行うにはハードルが高くなります。また、もし融資を行えても貸倒リスクをカバーするため、金利が高くなってしまいます。
このように民間の金融機関だけでは、カバーできない資金供給の役割を担うのが日本政策金融公庫などの政府系金融機関になります。
〇政府系金融機関
政府系金融機関は昭和の経済成長の時代に重要な役割を果たして、日本の経済の近代化の促進に大きく寄与しています。また、政府系金融機関は当初の役割を終えて時代に合う形に変更するための統合を進めています。
2008年に日本政策金融公庫は、国民生活金融公庫と農林漁業金融公庫と中小企業金融公庫が統合しています。さらに、2022年までに日本政策投資銀行と商工熊井中央金庫の2つは、民営化を予定しています。
現在ある政府系金融機関は4つです。その機関名称と役割は以下になります。
《4つの政府系金融機関》
①日本政策金融公庫
説明は後述するため、ここでは割愛します。
②日本政策投資銀行
日本産業界の国際競争力強化と、エネルギーの安定供給、産業構造転換支援などを推進することを目的として、「大口かつ長期投資」と「一体型金融サービス(融資・投資・コンサルティング)」を提供します。
③国際協力銀行
日本産業界の国際的な競争力強化や地球温暖化防止などの地球環境の保全を目的として、民間企業が取り組む国際大型プロジェクトや中小企業の海外事業展開の支援などを行います。
④商工組合中央金庫
中小企業の、中小企業による中小企業のための金融機関であることを機関の根幹においた、政府機関唯一の政府と民間による共同出資機関になります。
制度融資を支援するメインとして、経営サポートや地域の金融機関のサービスで行き届かない領域をカバーする役目を担います。
政府系金融機関はそれぞれの役割は異なりますが、その目的は日本の経済や産業の発展が含まれます。そして創業ならびに企業の発展は経済や産業の発展に寄与します。創業期だけではなく、事業を成長させていく時など支援が必要な際には、政府系金融機関の助けを借りる事が出来ないかを確認する事は重要です。
◯日本政策金融公庫で創業時に利用できる主な融資制度
日本政策金融公庫では、創業時に利用できる融資制度が複数あり、その中で主な融資制度を紹介します。
≪創業時に利用できる主な融資制度≫
①新創業融資制度
これから新規事業を開始する方、または事業開始から税務申告を2期終えていない方向けの融資制度になります。
②新規開業資金
これから新規事業を開始する方、またはおおむね事業開始から7年以内の方向けの融資になります。(ただし、生活衛生関係等の一部業種を除外)
③女性、若者/シニア起業家支援資金
これから新規事業を開始する方、またはおおむね事業開始から7年以内で、以下の3つの要件のいずれかに該当する方向けの融資になります。
・女性
・35歳未満(若手)
・55歳以上(シニア)
④生活衛生新企業育成資金
生活衛生関係*の事業を創業する方、または創業後おおむね7年以内の方向けの融資になります。
⑤資本性ローン
創業等に取り組む中小企業や個人事業主で、地域経済の活性化のために一定の雇用効果が見込まれる事業や地域社会に不可欠な事業や技術力の高い事業に取り組む方向けの融資になります。
⑥中小企業経営力強化資金
認定経営革新支援機関**の指導・助言を得ながら新事業の開拓を実施する方や、中小企業の会計に関する基本要領や指針に沿った会計処理を実施する方の資金調達強化を支援する融資になります。
*生活衛生関係とは、国民生活に欠かす事が出来ないサービスや商品を提供する、飲食業や理美容業やクリーニング業やホテルや旅館業などの18業種をいいます。
**認定経営革新支援機関とは、国が認定する一定以上の専門知識や実務経験をもって中小企業や個人事業主の経営相談を受ける事ができる支援機関をいいます。
〇各融資制度の概要
新創業融資制度
新創業融資制度とは、日本政策金融公庫が行う創業時の企業・個人事業主向けの融資サービスです。新創業融資制度が利用できる要件には、“創業の要件”があります。新創業融資制度は創業者に対しての融資になるため、創業時の資金調達に不安がある場合も安心です。
≪新創業融資制度の利用の要件≫
①創業の要件
- ・新たに事業を開始する方
- ・事業開始後から税務申告を2期終了していない方
②雇用創出等の要件
- ・雇用創出を伴う事業を始める方
- ・現在勤める企業と同じ業種の事業を開始する方
- ・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を開始する方
- ・民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を開始する方
等の一定要件に該当する方をいいます。但し、事業を開始している場合も事業開始時に一定要件に該当する方も対象となります。
なお、新創業融資制度を利用した貸付金の残高が1,000万円以内である場合、雇用創出等の要件を満たす事が出来ます。
③自己資本の要件
- ・新たに事業を開始する方、または事業開始からの税務申告を1期終了していない方は、創業時に創業資金総額の10分の1以上の事業に利用される資金である自己資金を確認できる方
- ・但し、上記雇用創出等の要件の『現在勤める企業と同じ業種の事業を開始する方』と『産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を開始する方』は自己資本の要件を満たす事が出来ます。
新創業融資制度の使用用途は、事業を開始するため位に必要とする“設備投資”と事業を継続するために利用する資金である“運転資金”となっています。融資限度額は3,000万円で、そのうち分は1,500万円までが運転資金として借入が出来ます。
無担保無保証を希望する場合の基準利率は2.46%~2.75%となっています(令和2年4月1日現在)。金利で比較すると、後述する制度融資のほうが低く設定されています。しかし、本融資制度では連帯保証人が必要ないという点も特徴になります。
新規開業資金/生活衛生新企業育成資金/女性、若者/シニア起業家支援資金
新規開業資金とは、開業時ならびに開業後に必要とする設備投資ならびに運転資金のための融資になります。
融資限度額は7,200万円で、うち運転資金として利用できるのは4,800万円までとなります。
返済期間は設備資金であれば20年以内で、運転資金の場合には7年以内になります。
利用できるのは以下の要件に該当する方になります。
- ・雇用創出を伴う事業を開始する方
- ・現在勤めている企業と同じ業種の事業を開始する方
- ・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
- ・民間の金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を開始する方
なお、新規開業資金の貸付金の残高が1,000万円以内の場合には、上記要件を満たす事ができます。
また、利率は基準利率が2.16%~2.45%で特別利率AからCの3パターンがあります。詳細は日本政策金融公庫のホームページで確認できます。
なお、新規開業資金は生活衛生関係の事業を営む方を除外しています。それは、生活衛生関係の事業を営む方は同様の条件で『生活衛生新企業育成資金』を利用できるためになります。また、生活衛生新企業育成資金は設備投資を用途とする場合には7,200万円から4億8,000万円を融資限度額としています。
同様に、融資要件を女性または35歳未満の若者と55歳以上のシニアに利用者を限定しているのが、『女性、若者/シニア起業家支援資金』となります。借入用途や融資限度額などは新規開業資金と同様になります。
資本性ローン(挑戦支援資本強化特例制度)
資本性ローンの特徴は、出資に近い形で資金を調達する事ができる点です。通常、融資を受けるとそれは負債となりますので、負債が多いと財務体質に不安を持たれてしまいますが、資本性ローンではその心配がないという事です。
資本性ローンは以下の二つの制度があります。
- ①国民生活事業…融資限度額が4,000万円の創業時の利用がメインになる制度
- ②中小企業事業…融資限度額が1社あたり3億円の地域活性化や地域社会に根差した事業者向けになる制度
上記の国民生活事業においては、「技術やノウハウに新規性がみられる」「公的ファンドから出資を受けた創業7年以内の企業」などが対象となります。また、融資機関は5年から15年で、返済方法は毎月の支払いは利息のみで最終支払い時点で元金を一括で支払する“期限一括償還”方式になります。
中小企業経営力強化資金
中小企業経営力強化資金は、認定支援機関の経営支援や事業サポートを受けながら新事業分野に挑戦する企業が対象の融資制度になります。
対象となるのは以下の2項目のどちらかに該当する企業になります。
①次の全てに該当する
- ・経営改革又は異分野中小企業と連携を行い、新事業分野の開拓等を通して市場の創出や開拓を行おうとする企業
- ・事業計画を自ら策定し、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関の指導やアドバイスをうけている事
②次の全てに該当する
- ・中小企業の会計に関する“基本要領”または“指針”を適用するか適用する予定のある企業
- ・事業計画書を自ら策定している
融資は、策定した事業計画の実行に必要な設備資金と運転資金を上限7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで利用出来ます。また、設備資金は20年以内、運転資金は7年以内の返済期間となります。
1-4 制度融資
制度融資は、創業時期の中小企業を支援する、地方自治体と信用保証協会と金融機関が連携して行う融資制度になります。具体的には金融機関から融資を受けるには不足してしまう信用度の部分を、信用保証協会が保証し、地方自治体が金融機関に利息部分を信用保証協会に保証料を一部支払いする事で補います。
制度融資に関わる機関は、『地方自治体』『信用保証協会』『金融機関』の3つになります。それぞれの役割があって、制度融資が成立しています。
地方自治体
地方自治体とは、地方公共団体とも呼ばれる日本の都道府県や市区町村を統括する行政機関です。各地方自治体には、地域経済の活性化のために“新規開業”や“雇用創出”を支援する融資制度があります。制度融資では地方自治体は融資を行う事はありません。融資を行う金融機関に利息補助などを通じて制度融資をあっ旋しています。
信用保証協会
信用保証協会は、中小企業ならびに小規模事業者の金融円滑化を目的として、金融機関に対して債務の保証を行う信用保証制度を提供しています。また、保証協会法にもとづいて設立されている公的な機関です。
金融機関
金融機関は、制度融資において主に審査と融資を実施する役目を担います。制度融資でも通常の融資と同様に、金融機関の審査で融資を受ける事が出来ない場合があります。
〇制度融資の商品概要
制度融資は各地方自治体によってその内容の詳細は異なります。そのため、一例として東京都が新規の創業資金ならびに創業後の事業資金に活用できる『創業融資』の商品概要を紹介します。
対象となるのは以下の3項目のいずれかに該当する企業になります。
①創業前
まだ事業を開始していない場合で、“個人として1ヶ月以内”か“会社設立して2ヶ月以内”に東京都内に創業する具体的計画があり、かつ東京都が設定する「ご利用いただける方」の2から4の条件を満たしている方
②創業後
「ご利用いただける方」の全条件を満たして、創業日から5年未満の中小企業者および組合*
③分社化
「ご利用いただける方」の全条件を満たして、東京都内で分社化する具体的な計画がある、もしくは分社化後5年未満の会
融資は、策定した事業計画の実行に必要な設備資金と運転資金を上限7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで利用出来ます。また、設備資金は20年以内、運転資金は7年以内の返済期間となります。
2 日本政策金融公庫の3つのメリットと1つのデメリット
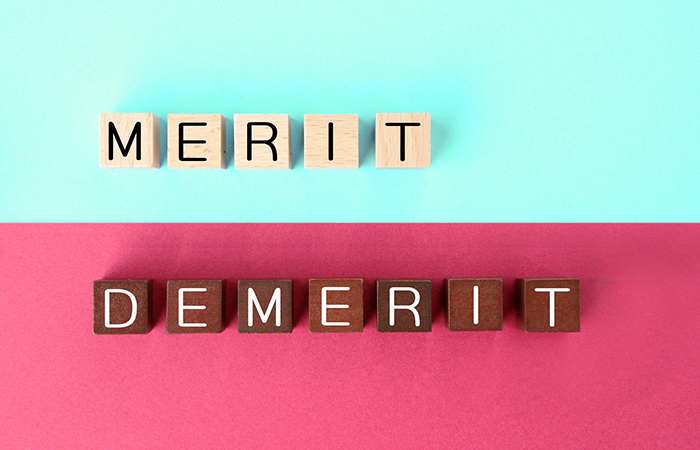
日本政策金融公庫を活用するメリットとデメリットを紹介します。

メリットは大きく以下の3つになります。
- ①融資を受ける事が出来やすい
- ②創業時に必要なノウハウやアドバイスが受けられる
- ③資金調達のコストが抑えられ、無理のない返済ができる
また、注意しなければいけない点ともいえるデメリットもあります。
- ①融資を受けるまでの期間が長くなってしまう
2-1 融資を受ける事が出来やすい
事業実績の乏しい創業時期における中小企業の資金調達においては切実な問題は、借りられるか借りられないかという点です。
日本政策金融公庫の融資は、創業融資であっても可決率が高いという特徴があります。日本政策金融公庫の重要な役割の一つが、中小企業や個人事業主などの規模の小さい企業の資金不足を融資によって解消していくことにあるからです。
また、日本政策金融公庫の融資を受ける事で、副次的な要素として他の金融機関の融資を受けられる可能性が高まります。一般的に金融機関が重視するのは、実績です。そのため、日本政策金融公庫の融資が降りた事ならびに返済を一定期間適切に実施していることが重要な実績になります。
2-2 創業時に必要なノウハウやアドバイスが受けられる
日本政策金融公庫の基本理念及び経営方針には、「お客様の立場に立って親身に応対し、身近で頼りになる存在を目指す」とあります。
日本政策金融公庫は国内の中小企業や個人事業主の3割以上に支援を行っています。つまり、現在時点でも126万先の中小企業と事業者と融資や信用保険で取引を行っています。そのため、中小企業の融資や資金繰りについては大きなノウハウが蓄積しています。また、新事業支援などの成長戦略分野への支援を行っており、金融を通じて中小企業者の成長と発展を支えています。
また、金融支援の他にも「顧客支援サービス」も提供しています。顧客支援サービスとは、財務書類の精査とお客様との対話と現場に足を運ぶという“公庫のDNA“を活用し、ここの企業の経営課題を対話の中で見つけ、企業や事業の発展に必要な情報提供やアドバイスを行っています。また、課題によっては外部専門家を紹介する事も可能です。
2-3 資金調達のコストが抑えられ、無理のない返済ができる
資金調達時に考えなければいけない1つが、利息負担になります。利息負担が資金調達のコストになります。資金調達のコストが、資金調達のメリットを超える場合は借りてはいけません。しかし、前述のとおり融資が下りないと困るという状況の場合には、審査が下りると資金調達のコストの事を軽視しがちになってしまいます。
資金調達コストを軽視する事が積み重なると、利息部分だけを支払いする資金力のみになった結果元金が減っていかないという“悪い財務状態”にもなりかねません。そのため、金利はできるだけ抑える事が求められます。また、返済負担を軽減するためには返済期間が長いというのも重要な要素になります。
日本政策金融公庫の創業融資の金利は、2%前後になります。これは、民間の金融機関と比較すると、圧倒的に低い金利です。創業時は貸倒リスクが高いため、融資を簡単に受ける事が出来ません。また、出来たとしても金利が高くなります。その結果、民間の金融機関でも5~10%程度となりますし、ビジネスローンを提供する消費者金融などのノンバンク系であると15%前後になります。
具体的に500万円を元金均等方式で10年間の支払をした場合に、年率1%の金利は約25万円になります。仮に、上記と同じ金額を同じ期間で日本政策金融公庫(金利2%)とノンバンク(金利15%)で融資を受けた場合、325万円の調達コストに差が出てくることになります。
さらに10年などの返済期間が設定できる点も無理のない返済につながる要素になります。支払い期間が倍になれば、元金の返金負担は半分になります。
また、長年経営を行っていく中で資金繰りが厳しくなる時期が来る場合もあります。そのような時期には、毎月予定してきた返済が難しくなります。そのような場合に助かるのが、『減額申請』があります。減額申請をする事で、返済方法や返済金額の変更が検討できれば、無理のない返済が実施できます。そして、資金繰りが安定してきた際には、契約時の返済計画に戻す事も可能です。
2-4 融資を受けるまでの期間が長くなってしまう
日本政策金融公庫の審査時間は、長くなっています。ノンバンクの消費者金融機関であれば最短1日から数日で結果を返します。銀行などの金融機関は1~2週間です。日本政策金融公庫では数週間から1ヶ月という期間が必要とされています。
一般的には、金利が高い貸付の場合審査が短くなります。そのため、15%程度の金利をとるノンバンクが最も審査期間は短く、続いて金融機関で、最後に日本政策金融公庫が最も長くなる事は当然とも言えます。また、創業融資で利用できる新創業融資制度では、連帯保証人が不要になる場合もあります。つまり、金利を低く設定し、できるだけ融資を受ける側に負担がかからない方法で融資を行うために、慎重に審査を行うという理解を持つと審査時間が長い事も納得できます。
いつ資金が必要なのかあらかじめ逆算して、日本政策金融公庫の融資申し込みを行う事をお勧めします。
3 制度融資の2つのメリットと2つのデメリット

制度融資のメリットとデメリットもまとめますが、創業時の中小企業者に融資を行うという点で根本のコンセプトが類似しているため、メリットとデメリットも似ています。

メリットは大きく以下の2つになります。
- ①融資が受けやすい
- ②金利が安い・補助制度もある
また、デメリットも2つになります。
- ①申込から融資実行まで2~3ヶ月程度もかかるなど、手続きは煩雑
- ②自己資金要件や連帯保証人を求められるケースもある
3-1 融資が受けやすい
日本政策金融公庫と同様に、創業時の実績がない中でも融資を受ける事ができやすいというのが、最大のメリットになります。
制度融資は地方自治体が主体である部分も多く、それゆえに地方経済の活性化につながる企業の創業についてはプラスに見てくれます。創業した企業が活躍してくれれば、雇用が創出される事や、法人事業税や法人住民税などの地方税の納税を受ける事ができるからです。
地方自治体はその地域の経済や力関係を熟知している場合が多く、自治体とのすり合わせの中で、信用保証協会によくみられるための様々なヒントや、その地域ならではの事業成功の独特のノウハウを得られる場合もあります。
3-2 金利が安い・補助制度もある
制度融資の金利の低さは、日本政策金融公庫の新創業融資制度の金利を下回ります。詳細は各自治体によって異なりますが、地域によっては年利1%以下の固定金利などもある事は、資金調達コストを抑える事ができるため大きなメリットになります。
また、一定期間は金利を支払いせず元金のみの支払いを行う据え置き期間が設定できる制度融資もあります。据え置き期間がある事で、毎月の支払金額自体を抑える事ができるので、事業立ち上げの時などには非常に助かります。加えて、自治体によっては信用保証協会へ支払する保証料の一部や金融機関への金利の一部を補助する補助制度がある場合もあります。
制度融資は各地方自治体で異なります。好条件の制度融資を作っている自治体は、企業誘致に力を入れている証になります。そのため、多くの企業が創業している地域は経済も活性化しやすく、創業後の経営についてもプラス面が多くなる事も見落とす事が出来ません。
3-3 申込から融資実行まで2~3ヶ月程度もかかるなど、手続きは煩雑
申込してからの審査期間が長いのは、デメリットになります。制度融資においては、地方自治体と信用保証協会と金融機関のそれぞれが独立した組織であるため、それぞれで審査基準を設けて審査を行います。そのために、申込プロセスが長くなり、手続きが煩雑になります。
当然各地方自治体や融資を受ける企業によって異なりますが、制度融資において申込から融資実行までは2~3ヶ月かかるのが一般的です。そのため、新創業融資制度の利用と同じく計画的に前もって申込を行う事が必須になります。
3-4 自己資金要件や連帯保証人を求められるケースもある
自己資金割合に対して融資額を決定する自己資金要件がある自治体も多くあります。場合によっては、自己資金の2倍までの融資限度額に設定される自己資金要件がある事もあります。そのため、自己資金が大きく不足している時などに利用しにくいというデメリットになります。新創業融資制度では、自己資金要件は融資額の10/1と低めの設定になっていて、前職と同じ業種であれば外す事も可能です。
また、新創業融資制度では不要な連帯保証人を制度融資では必要とする条件になっている場合が多い点もデメリットになります。
4 日本政策金融公庫と制度融資の手続き

日本政策金融公庫の新創業融資制度と制度融資の手続きをそれぞれ紹介します。
〇新創業融資制度の手続き
新創業融資制度の申込から融資実行までの流れは以下になります。
①融資相談
相談は各支店の融資相談係に電話もしくは直接問い合わせを行う事が出来ます。融資の条件や必要書類について問い合わせを行う事が必要です。
②申込
以下の6つの申込書類を郵送ないしは窓口へ提出します。借入申込書と創業計画書と月別収支計画書は提出書類ならびに記入例はダウンロードが出来ます。
≪申込必要書類≫
- ・借入申込書
- ・創業計画書
- ・月別収支計画書
- ・履歴事項全部証明書原本
- ・(設備投資を行う場合)見積書
- ・(不動産担保申込の場合)不動産登記簿謄本または登記事項証明書
③面談と実地確認
申込が受領されると、審査担当者と面談を行います。審査担当者は創業計画が実現できるだけの真剣さや必要知識があるかなどを確認していきます。重要な事は全体を記憶する事ではなく、事業を成功させるポイントをおさえておく事が必要です。
また、審査担当は店舗や事業予定地や申込者の自宅などを実地確認します。
④融資実行
審査結果は面談・実地確認後1週間程度で審査結果通知が郵送されます。融資可能の場合には借用証書も同封されます。融資実行に必要な以下の書類を同封して返送します。不備がなければ返送後1週間程度で融資が実行されます。なお、融資実行後に支払明細書が郵送されます。
≪借用必要書類≫
- ・借用証書
- ・預金口座利用届(複写式)
- ・発行後3ヶ月以内の印鑑証明(借入人と連帯保証人のもの)
- ・融資金の指定振込先の口座通帳の表と2面コピー
- ・その他指示があった書類
〇制度融資の手続き
制度融資の申込から融資実行までの流れは以下になります。
①融資申込
申込者は各地方自治体が指定する融資申込書を、事務所住所を管轄する商工会等の受付機関に申込します。なお、申込必要書類は各地方自治体によって異なりますが、各地方自治体のホームページからダウンロードができる場合もありますので、ホームページの確認や事前の電話相談を行う事も可能です。
②受付機関審査
各地保自治体は、申込内容を確認し、店舗や事務所や代表者自宅などの現地確認を行い、申込が適切と判断できる場合には受付を行います。
③金融機関申込
申込者は、受付機関が受付した融資申込書で金融機関に申込を行います。この際にも各金融機関に事前に申込必要書類を確認して、用意しておく事を忘れないでください。また、申込を行った後に各金融機関に契約時に必要な書類についても確認しておきます。
④金融機関による審査と保証依頼
金融機関は、申込者の審査を行います。審査が通った場合には、信用保証協会へ保証の依頼を行います。
⑤信用保証協会の審査
保証依頼をうけた信用保証協会は、申込者の保証の審査を行います。審査が通った場合には、信用証書を金融機関へ交付します。
⑥金融機関からの融資
金融機関は金融機関が定めた融資契約に必要な書類を受け付けたのちに、各地方自治体が定めた条件に沿って申込者への融資を実行します。
5 政府の新型コロナウイルス感染症に係る経済対策の概要
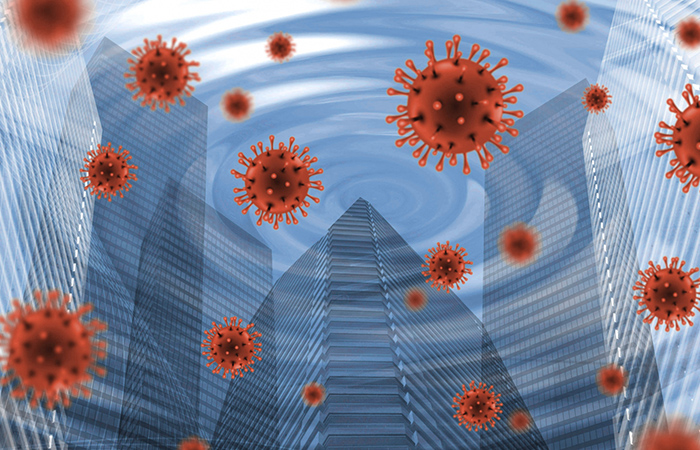
改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき、2020年4月7日に政府は緊急事態宣言を発出しました。経済活動が停滞する中、中小・小規模事業者を中心に混乱が広がっており、事業の継続へ向けた喫緊の対応が求められるところです。そこで政府の緊急経済対策の概要とともに、補助金や助成金等の活用についても併せてご紹介しておきます。
日本政府は、緊急事態宣言発出とともに「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を閣議決定し、具体的な施策内容を公表しました。雇用の維持と事業の継続が喫緊の課題といえますが、企業の事業活動に関しては、「雇用の維持」、「資金繰り対策」「事業継続困難事業者支援」、「税制措置」の4つの項目に整理して施策を示しています(公表文書には、このほかに「生活困窮世帯や個人への支援」が含まれますが、ここでは説明を省きます)。
「雇用の維持」では、従来から措置されている「雇用調整助成金」の特例措置の更なる拡大、新卒応援ハローワークにおける内定取消者に対する特別相談窓口設置や外国人労働者等を含めた求職者等相談支援体制の強化策が中心となります。
「資金繰り対策」では、日本政策金融公庫等による特別貸付や、中小・小規模事業者に対する実質無利子資金の融通・借換等の支援策が、「事業継続困難事業者」に対しては、セーフティーネット構築を目的とした持続化給付金(仮称)という新たな給付金制度の創設や、現行事業である「中小企業生産性革命推進事業」の特別枠の創設等が措置されています。
「税制措置」に関しては、納税者対策として、納税猶予制度の特例、欠損金の繰戻しによる還付特例、償却資産等の固定資産税および都市計画税の軽減措置が講じられていますが、この記事では説明を省きます。以下、それぞれの支援策について解説します。
6 雇用の維持に係る補助金等の対策

雇用維持対策では、求職者向けの支援策が多い中、中小・小規模事業者に対する支援策として、厚生労働省所管の「雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大」が措置されました。雇用調整助成金は、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。平成30年北海道胆振東部地震、平成30年7月豪雨、令和元年の台風19号に続き今回の措置となりましたが、雇用調整助成金制度および今回の追加特例措置の内容は次のとおりです。
|
この助成金は、「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1および2を実施した場合に受給することができます。 |
||||||||||
| 雇用調整項目 | 内容 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)休業 |
次の1)~5)のすべてに該当する休業を行うこと
|
|||||||||
| (2)教育訓練 |
次の1)~5)の全てに該当する教育訓練を行うこと
|
|||||||||
| (3)出向 |
次の1)~13)のすべてに該当する出向を行うこと
|
|||||||||
| 対象事業主 |
本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。 |
|||||||||
| (1)共通要件 |
各雇用関係助成金に共通の要件等(省略)のAの要件に該当するとともに、Bの要件該当していないこと。そのうえで、次の点に留意しなければなりません(AとBの要件については、厚労省のパンフレットでご確認下さい)。 |
|||||||||
| (2)個別要件 |
|
|||||||||
| (3)状況要件 |
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により「事業活動の縮小」を余儀なくされたものであること。事業活動の縮小とは、次の1)または2)の要件を満たす場合をいいます。 |
|||||||||
| 支給額 |
次の1の「対象期間」に、期間中に行われた休業、教育訓練または当該期間中に開始された出向(ただし3カ月以上1年以内の出向に限る)について、2によって算定された額が支給されます。 2 支給額
|
|||||||||
事業所における賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいいます。
休日等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。
(1)新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者についても助成対象となります。
(2)過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について
前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします。
7 資金繰り対策としての施策

資金繰り対策は、利子補給方式が中心で、新規融資のほか、既往債務の無利子融資への借り換え等が可能です。融資とは言え、実質無利子となる利子補給方式は補助金と同様の効果を生みます。各種支援策の中から、ここでは「無利子・無担保融資」の概要について解説します。
これは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「危機対応融資」等に「特別利子補給制度」を併用して実質無利子化とするものです。このうち、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」については次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資対象 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的に業況が悪化し、次の(1)または(2)のいずれかに該当する事業者 |
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 担保 | 無担保 |
| 貸付期間 | 設備資金:20年以内、運転資金:15年以内 (うち据置期間は5年以内) |
| 融資限度額 | (注2)中小事業3億円、国民事業6,000万円 |
| 金利 | 当初3年間の基準金利を▲0.9%(中小企業事業:1.11%⇒0.21%、国民事業:1.36%⇒0.46%)とし、4年目以降は基準金利 |
1.適用対象
上記の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「商工中金等の危機対応融資」により借入れを行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者等のうち、以下の要件を満たす方
(1)個人事業主(事業性のあるフリーランス含む):要件なし
(2)小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少
(3)中小企業者(上記2者を除く):売上高20%減少
2.利子補給
(1)期 間:借入れ後当初3年間(引き下げ後金利負担分)
(2)補給対象上限:中小事業1億円、国民事業3,000万円、危機対応融資1億円
日本政策金融公庫が行う事業のうち、中小・個人事業の経営者が利用する可能性が高いのは「国民生活事業」と「中小企業事業」です。国民生活事業は、中小(特に小規模)事業者や創業企業への事業資金融資や子供の教育資金などを扱っています。中小企業事業は、主に中規模以上の企業に対する事業資金融資および信用保険業務等を行っています。
8 事業継続困難事業者への支援

事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援策としては、新たな給付金制度として「持続化給付金(仮称)」、中小・小規模事業者の生産性向上策として既に措置されている「中小企業生産性革命推進事業」に特別枠を設けるとともに、相談体制の強化が図られます。ここでは、持続化給付金と中小企業生産性革命推進事業特別枠について、令和2年度補正予算が成立することを前提として現状で判明している事項を紹介します。
8-1 持続化給付金
給付対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者について、中堅(注1)・中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付するというものです。
会社規模の区分については、法令で定義されたもののほか、実務上使用される区分もあります。主な会社区分は次のとおりです。
| 大会社(大企業) | 中堅企業 | 中小企業 | 零細企業 | |
|---|---|---|---|---|
| 会社法 | イ.資本金5億円以上ロ.負債の額200億円以上※上記のどちらかに該当 | 区分なし | 大会社以外 | 区分なし |
| 法人税法 | 資本金1億円超 | 区分なし | 資本金1億円以下 | 区分なし |
| 実務上の区分 | 資本金10億円以上 | 資本金1億円以上10億円未満 | 資本金1千万円以上1億円未満 | 資本金1千万円未満 |
8-2 中小企業生産性革命推進事業
中小企業生産性革命推進事業は、「ものづくり補助金」、「持続化補助金」、「IT導入補助金」の三つの事業で構成されています。これらの補助率または補助上限を引き上げた特別枠が新たに設けられることになりました。各事業の概要は次の通りです。
8-2-1 ものづくり補助金・・・補助率を2分の1から3分の2へ引き上げ
中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。
8-2-2 持続化補助金・・・補助上限を50万円から100万円へ引き上げ
小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援するものです。
8-2-3 IT導入補助金・・・補助率を2分の1から3分の2へ引き上げ
中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、PCやタブレット端末等のハードウエアのレンタル等を含めたITツールの導入を支援するものです。
9 まとめ
今回は、創業時に資金調達の代表例である日本政策金融公庫の融資と地方自治体による制度融資を中心として、創業時の資金調達に必要な情報を解説しました。
創業時には資金調達が簡単ではなく、融資実行をしてくれる機関があったとしても1ヶ月単位で時間がかかります。創業時に計画通りに物事が進まない事も多いのは事実です。だからこそ資金調達方法を一つでも多く確保すべきなので、ぜひ新創業融資制度や制度融資などの創業融資を計画的に申込し、必要な時に必要な資金調達ができるようにしてください。
また、補助金・助成金については、新設されるもののほか既往措置に感染症対策として特別枠を設けるなどして対策の幅を広げています。これに加えて融資制度も、基準金利の引き下げにとどまらず、要件次第では実質無利子となる利子補給制度を設けて補強しています。全ての措置を紹介できたわけではありませんが、この記事を参考に、自社の状況に応じた制度の活用を検討してみてください。